時代・地域別 数学史
このサイトの運営者


Fukusuke
数学史の先生
私立中高一貫校で教員をしながら、数学史の楽しさを伝えています。
✅ブログは累計200万PV突破
✅2冊の著書はどちらも1ヶ月で重刷決定
『イラストでサクッと理解 世界を変えた数学史図鑑』(ナツメ社)、『教養としての数学史』(かんき出版)
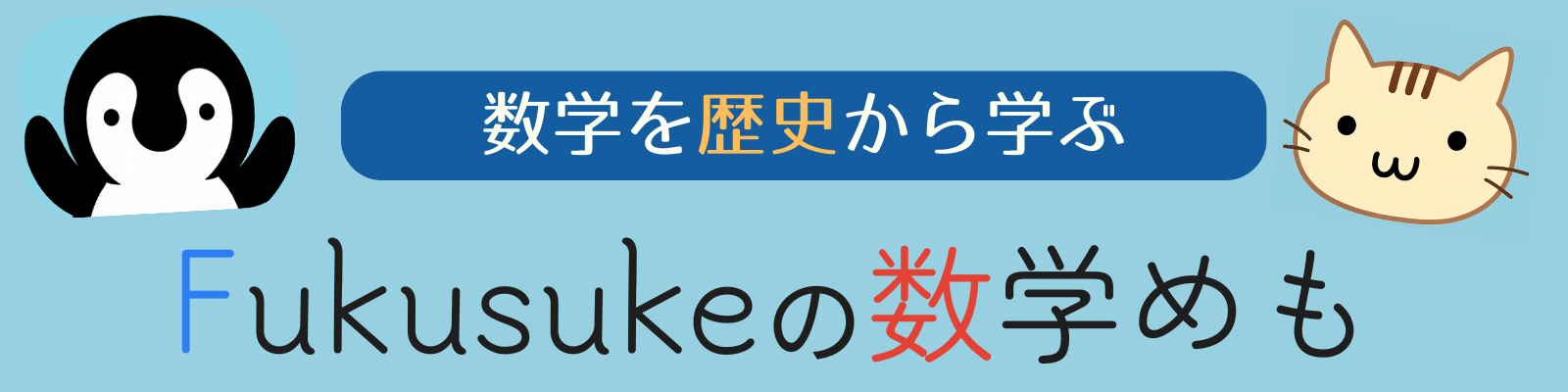


Fukusuke
数学史の先生
私立中高一貫校で教員をしながら、数学史の楽しさを伝えています。
✅ブログは累計200万PV突破
✅2冊の著書はどちらも1ヶ月で重刷決定
『イラストでサクッと理解 世界を変えた数学史図鑑』(ナツメ社)、『教養としての数学史』(かんき出版)